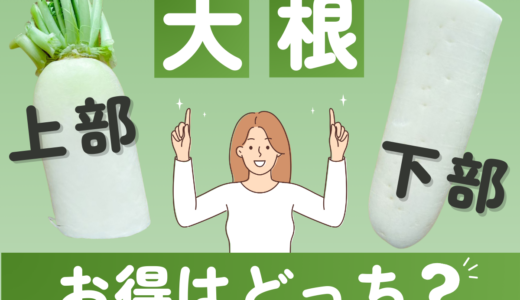夏野菜の代表格、オクラ。そのネバネバとした食感が特徴で、栄養価も高く、食卓に取り入れたい食材のひとつです。
しかし、「オクラのヘタって切ってしまっていいの?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?

この記事では、元スーパー青果担当者の経験をもとに、オクラの“見落としがちな下処理のコツ”をご紹介します。
ちょっとした工夫を加えるだけで、食感が良くなり、風味もアップしますよ。
オクラは「板ずり」してから調理するのが基本

まず、オクラの表面には細かな産毛がびっしりと生えており、そのまま調理するとザラついたり、舌にチクチクとした刺激を感じることがあります。
特にサラダや和え物など、素材の口当たりが際立つ料理では、この産毛が気になることも。
そこで行うのが、下処理の基本ともいえる「板ずり」です。
塩をまぶしてまな板の上で転がすことで、産毛が取れて表面がなめらかになり、見た目もつややかに。加熱後の色合いも鮮やかになり、見た目にもおいしく仕上がるのが魅力です。
【板ずりの手順】
1)オクラを洗う。
2)まな板の上に並べ、オクラ全体に塩(粗塩がベスト)をふる。

3)手のひらでやさしく転がし、産毛をこすり落とす。

4)水で洗い流し、水気をふき取る。

これをすることで、表面がなめらかになり、加熱時の色合いも鮮やかに仕上がります。
ヘタは「切り落とさず、面取り」するのがコツ

つい、オクラのヘタを根元から切り落としてしまう方も多いのではないでしょうか?
しかし、これはおすすめしません。
ヘタを切り落とすと、加熱時に中のネバネバ成分や旨みが流れ出てしまい、味がぼやけてしまいます。
また、本来はヘタの根元まで食べられるのに、切り落としてしまうことでその部分が食べられなくなり、結果として可食部が減ってしまいます。
【おすすめの処理方法】
1)ヘタの先端を少しだけカットする。

2)包丁でガクの角をぐるりと面取りする。


このひと手間が、オクラの美味しさを引き出す重要なポイントになります。
まとめ
- オクラの表面は塩で板ずりして産毛を取り除くことで、なめらかな食感に仕上がる
- ヘタは根元から切らず、角を面取りすることで旨みの流出を防ぐ
- ひと手間を加えることで見た目も風味もぐっとよくなる
ちょっとした工夫で、オクラの味わいが格段にアップします。ぜひ一度お試しください。
※本記事は筆者の経験および一般的な調理知識に基づいて構成しています。調理方法はご家庭の環境やお好みに応じてご判断ください。